IB教育の好事例
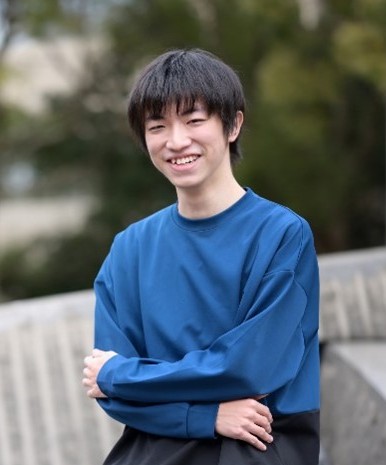
ぐんま国際アカデミー高等部 2023年3月卒
加藤 咲磨さん
ぐんま国際アカデミー高等部でDPを修了し、2023年3月に卒業。 現在は、横浜市立大学医学部医学科に在籍。
IBを通して身についた力
IBDPでは課題論文(EE※1)を仕上げ、各科目で探究課題(IA※2)に取り組まなければならないことに加え、プログラム全体にわたって課外活動(CAS)を継続する必要があります。IBプログラムを通じてこれらのタスクを滞りなくこなしていくために欠かせないマネジメントスキルが育まれ、大きなタスクと向き合うことに対する抵抗が小さくなったように思います。また、物理や化学のIAでは自分で実験を設計し、結果を表やグラフにまとめたのですが、この経験を通じて机上の知識にとどまらない科学的な思考力やリサーチマインドが身につきました。特に「これはIBならでは」と感じたのはアカデミック・インテグリティ(学術的誠実性)に対する意識が高まったことです。引用や参考文献の示し方について、ルールが徹底されていたため、文献の信憑性を吟味した上で出典を明記することが自然と習慣化しました。
※1:生徒が関心のある研究分野について個人研究に取り組み、研究成果を4,000語(日本語の場合は8,000字)の論文にまとめる(EE、課題論文)。
※2:IBDP教科の探究課題。所属校において評価が行われる(IA、内部評価課題)。
IBで身につけた力の活用
大学では課題や試験が立て込んで忙しくなってしまうこともあるのですが、そのような時でもIBで身についたマネジメントスキルを活かすことで部活などの予定と勉強を両立させながら乗り切れているように思います。また、実験レポートに取り組む際には、IAでの経験を活かして構成や図表の作成などを比較的スムーズに進められます。やや重めなレポートを課された際にも、EEを書き上げた経験があることであまり臆することなく向き合えますし、出典を記載することも含め、レポートの書き方で戸惑うことも少ないと感じます。また、EEやIAを書く上で英語論文を参照することもあったため、英語論文を読解し、その内容を発表する実習で論文読解スキルが活かせましたし、論文の引用が中心となって構成されている講義資料に対しても苦手意識を抱かずに学習できています。
TOK(知の理論)で学んだこと
TOKの授業で自然科学の知識の特徴について学習した際に、それらは様々な現象の観察によって創造されているため「帰納的」であることや、反証可能性があるため「暫定的」であることを教わり、言われてみればそうだなと納得する一方で、明文化されることで全く新たな学びを得たような感覚を覚えました。現在、私が学んでいる医学も知識が帰納的に創造されている学問なので、新しい発見によって常識が覆される可能性が大いにあると言えます。これを念頭に置くことで、最新の知見に対する意識が高まり、定説を疑うことで自分自身が新たな知識を創造するきっかけにも繋がると思います。
芸術の知識の特徴は、TOKの授業だけでなくEnglishAの授業でも学びましたが、他の知識の領域とは異なり、専門家でなくても作品を解釈することで知識を創造できるという視点が新鮮でした。私は音楽の演奏・鑑賞を趣味としているのですが、自分も知識の創造に関わっているのだと思うと、アマチュアとして音楽と向き合うことに対してさらに大きな可能性を見出せるようになりました。
CAS(創造性・活動・奉仕)で印象に残っていること
CASでの取り組みの中で最も印象に残っているのは、ピアノの練習・演奏を継続するという活動の延長で、自らコンサートを開催したことです。最初にこの案が出たのは家族内での会話で、その時には本当に実現させることまで考えていませんでしたが、思い切って実行に移したところ
大きな反響をいただくことができ、「挑戦する人」という学習者像を体現できたと感じました。今年度の初めには第三回のコンサートを開催し、大学で知り合った人も来てくださったり、これを機に様々な演奏会やラジオに出演する機会をいただけたりしているため、一歩踏み出したことが今の自分に与えた影響は非常に大きく、多岐にわたっています。
また、CASプロジェクトに関しては簡単に説明すると校歌の楽譜を整えたり、音源・映像を作成したりするサービスを提供したのですが、長期間にわたって他者と協力して計画を進めていく過程でその難しさや意義を改めて認識する機会となりました。
大学受験や進路選択で意識したこと
小学生の頃から、体の仕組みや病気、その治療について漠然とした興味を持っていました。中学から高校にかけて進路を考える中で、人の命を助けることに直接貢献できるという点に惹かれ、医学の道を志すようになりました。 私はIBDPの認定を受けた小中高一貫校に通っていたた
め、いずれはIBプログラムへ進むだろうと考えていたのですが、その場合には一般受験に向けた勉強との両立は難しいだろうと判断し、総合型選抜やIB入試の中でも学力試験や共通テストを課していない大学に志望校を絞りました。この選択によってIBの課題や勉強に集中できるようになった一方で、確実に高いIBスコア(※3)を取らなければならないことになったため、大学の出願要件や各科目の特徴、自分との相性を吟味してIBの科目選択を行いました。個人的には理系科目の方が理解できれば安定して高いスコアを取れると感じたため、HLは数学・物理・化学で固め、これらの科目では絶対に7を取るという目標の下、勉強に励みました。
※3:6教科それぞれ7点満点で、EEやTOKを加えて最大45点まで評価される
今後のキャリアについて
正直まだどの診療科に進むかなど、具体的なキャリアは思い描けていないのですが、臨床と研究のどちらか一方に縛られるのではなく、どちらも両立できるようなキャリアを目指しています。
先述のように、私が医学の道に進もうと決めたのは人の命を助けることに直接貢献したいと思ったからなので、臨床医として目の前の患者さんを治療し、その成果を自分の目で見届けたいという思いもあります。その一方で、TOKの授業で得た学びとして挙げたように、医学の知識は変化し得るという意識を持つことで、研究医として自分自身が新たな知識を創造していくのも魅力的だなと考えるようになりました。
大学の講義を通して、多くの疾患に対する根本的な治療法がまだ確立されていないことを知った今、臨床に携わりながらもその中で直面した医療の限界を突破するべく研究にも従事できるキャリアが理想的なのではないか、という考えに至っています。これもIAを通じてリサーチマイ
ンドが涵養されたからこそ至った考えだと思うので、IBでの様々な学びや経験が将来のビジョンに影響していると言えます。
IB校での学びの環境や人との関わりで、印象に残っていることは?
大学生になった今、IB校での学びの環境について振り返ると、ディスカッションやグループワークなどを通したインタラクティブで主体的な学びの機会がいかに多かったのか、ということに気付かされました。また、IBスコアは自分の周囲の人の成績に影響されるわけではなく、全世
界のIB生が共通の基準で評価されることから、スコアの競争で緊張感が走るというよりは、お互いに協力し合う雰囲気が強かったように感じます。私自身、同級生から質問を受けることもあったのですが、それらに答えることが自分自身の勉強にもなっていた実感があり、実際このように
アウトプットを通して学習するのは効果が大きいと言われているため、競争より協力というIB校の雰囲気は効果的な学習にも繋がっていたのだと思います。また、全国的に見てまだIB生は希少なので、お互いにIB生であるというだけでも仲間意識のようなものが芽生え、学校の垣根を越えて助け合えるということもIBならではの関わりだと感じました。
