IB教育の好事例
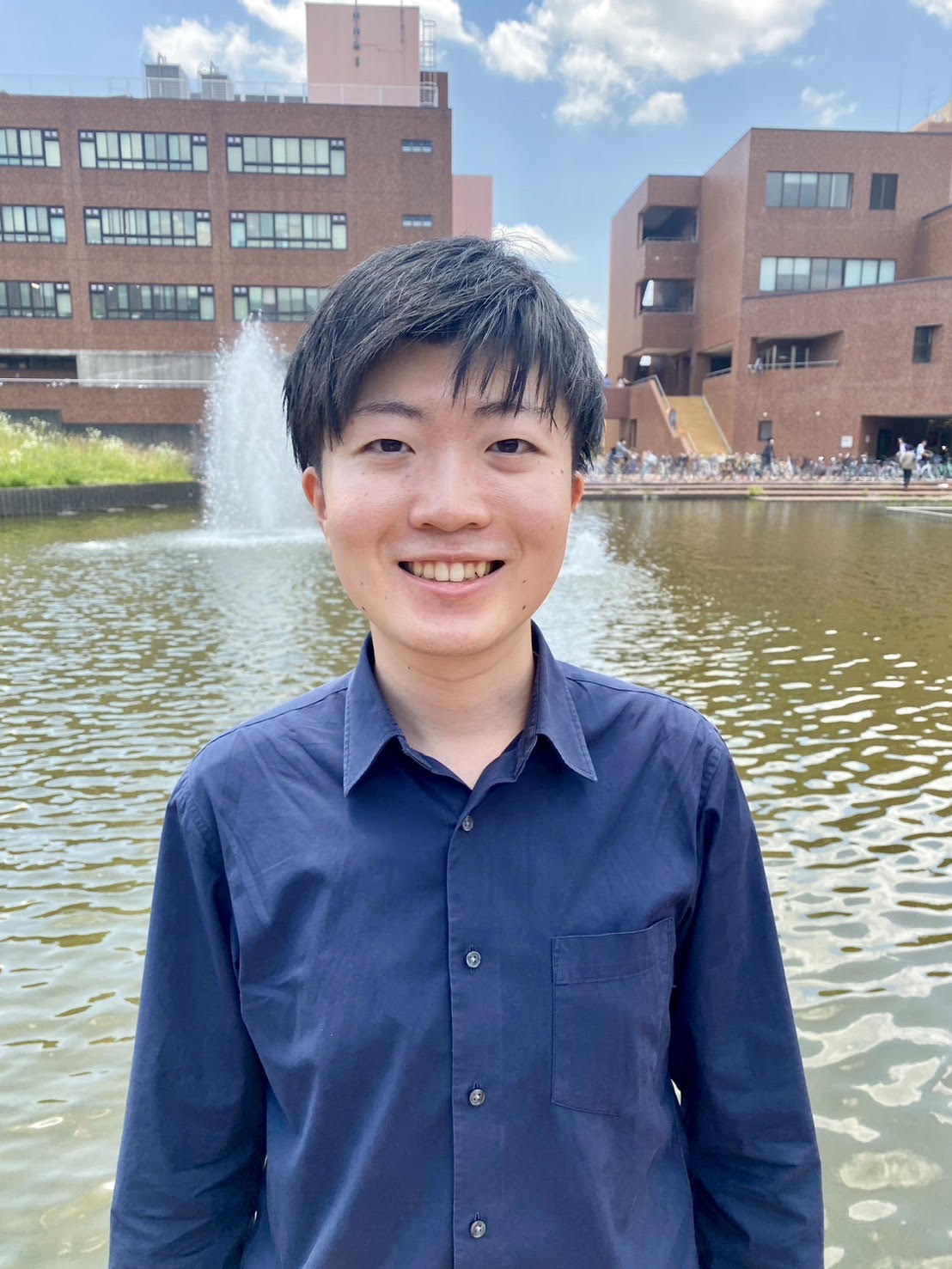
加藤学園暁秀中学校・高等学校 2018年3月卒
駒走 聡俊さん
加藤学園暁秀中学校・高等学校にてMYPとDPを修了し、2018年3月に卒業。都留文科大学に進学し国際教育学を学ぶ。在学中に、博報堂教育財団 教職育成奨学金の第4期生に採用される。その後、筑波大学大学院で教育学の修士号を取得し、現在はK. International School TokyoでセカンダリースクールのJapanese teacherとして勤務している。
IBを通して身についた力
IBの学びを通じて、主に2つの力が身につきました。1つ目は、「責任をもってやり抜く粘り強さ」です。特にDPでは、机上の学びだけではなく、CASを通して創造性や奉仕の心、健康的な生活を意識した活動にも取り組む必要がありました。学業と課外活動の両立は、まさにトライアスロンのように体力と集中力が試される挑戦であり、その経験を通じて、最後までやり遂げる粘り強さが身につきました。
2つ目に身についたものは、「他国の文化や他者の価値観を受け入れられる心」です。授業で多様な背景を持つ仲間と対話する中で、異なる価値観を尊重する姿勢が養われました。この経験は、大学の交換留学でスウェーデンに行った際にも活かされ、異文化に柔軟に適応できただけでなく、日本とはどのような国なのかを改めて見つめなおす機会にもなりました。その結果、日本人としてのアイデンティティ形成にも繋がったと感じています。
IBで身につけた力の活用
現在の職場であるインターナショナルスクールでJapaneseを指導する際に、IBで培った「自身の考えを言語化し、要点をまとめて伝える力」が大いに役立っています。これは、MYPやDPのカリキュラムで学んでいた際に、実験レポートやエッセイなど、論理的な説明が求められる課題に繰り返し取り組む中で自然と身についた力だと感じています。特にIB Japaneseの教員には、文学や言語を文化的背景と結びつけて考えさせ、その理解を通じて学びを広げる指導が求められます。単に生徒を「説得」するのではなく、生徒自身が「納得」できるように導くことを意識し、文学を学ぶ意義や、当時の時代背景と作品テーマの関連性を伝える際に、IBでの学びが生かされていることを強く実感しています。
TOK(知の理論)で学んだこと
TOKの学びを通じて、私は「物事を疑い、根拠を問う姿勢」を身につけると同時に、「知識は分野や文脈によって成り立ちや価値が異なる」という視点を得ました。特に印象的だったのは、「時間の経過とともに知識は正確になるか」というTOK小論文の課題です。天気予報のように、科学技術の進展によって正確さが増す分野がある一方で、一部の部族ではいまだに祈祷や踊りなどの民間療法を行っています。それらは現代科学の基準では「正確ではない」と見なされがちです。
しかし、その地域や文化にとっては精神的支えや社会的結束を生む大切な知識として存在しており、文化や伝統の中では「正確さ」よりも「意味」や「共同体とのつながり」が重視される知識もあることを学びました。こうした学びを通じて、私は知識を多面的に捉え、日常生活でも情報の背景や文脈を意識するようになりました。また、自分とは異なる価値観にも敬意を払い、その根底にある考えや背景を想像する姿勢を大切にしています。
CAS(創造性・活動・奉仕)で印象に残っていること
CASで取り組んだ活動の中で、特に印象に残っているのは、図書委員会の委員長として学内バザーで古本市を開催したプロジェクトです。古本の収集・整理、価格設定、シフト表の作成、会場レイアウトの工夫に至るまで幅広い業務を担当しました。実施にあたっては、限られたスペースや時間の中で企画を実現させるために、学校の先生方との交渉や調整も必要でした。こうした経験を通じて、相手の立場を理解しながら意見を伝える対話力や、協力関係を築くためのコミュニケーション力が養われたと感じています。この経験は、現在の職場でも多様な立場の人々と協働しながら業務を進める際に、大きな支えとなっています。
大学受験や進路選択で意識したこと
大学受験や進路選択の過程で最も意識していたことは、IB教員になるという夢を実現できる大学を選ぶことでした。しかし、その重要性を真に自覚したのは、最初の大学受験で失敗してからです。最初に受験した大学は、出願要件が合っているからと安易に志望校として選択してしまい、結果的に不合格となってしまいました。
その後、改めて自分が大学で学びたいことや将来の夢を見つめなおすことを決意し、IB教員を目指すために何を学ぶ必要があり、どの大学が最も自分に合っているのかを再考しました。その結果、文系学部として日本で初めてIB教員養成コースを設けた、都留文科大学への進学を決めました。在学中は、国内外のIB校において実習を経験し、IB生への指導法やメンタルケアに関する知識を深めることができました。
進学先と自分の将来の夢を照らし合わせ、粘り強く妥協のない選択をしたことで、大学での学びが非常に充実したものになり、IB教員になりたいという長年の夢を実現できたと思っています。
今後のキャリアについて
現在Japaneseの教員として、文学を通じて生徒が自己と向き合い、他者の視点を理解する力を育む指導をすることにやりがいを感じています。今後は、教科指導にとどまらず、進路指導にも積極的に関わり、生徒一人ひとりが自身の価値観や将来像と向き合い、納得感のある選択ができるよう支援していきたいと考えています。
進路選択は、単なる進学先の決定ではなく、自分の価値観や将来のあり方と向き合う重要な機会です。IBで培われる「自ら問いを立てて、考え、表現する力」は、そのプロセスを力強く支える土台になると実感しています。だからこそ、私は生徒が「どの大学に行くか」ではなく、「どのように生きたいか」という視点で進路を捉えられるような対話を重ね、学びと進路の両面から生徒の成長を支えていきたいと考えています。
IB校で過ごしたなかで、特に心に残っていることは?
IB校での学びの環境で特に印象に残っているのは、教室空間のつくり方です。これは、大学進学後に実習を通じてIB校と一般的な日本の学校の両方を経験し、改めて気づいたことでもあります。IB校では、教室のレイアウトや机・椅子の形状に至るまで、生徒の主体的な学びや対話を促すような工夫が随所に見られました。また、壁には多言語の新聞やサマーキャンプの案内、生徒のプロジェクトの成果物などが掲示されており、学びへの興味関心を広げる環境が整っていました。IBで学んだ当時は当たり前に感じていたこのような環境が、生徒の探究心や国際的な視野の育成を自然と後押ししていたのだと、実習を経て改めて実感しました。
最後に:恵まれた学びの環境への感謝
IBでの学びを振り返ったとき、私が強く実感したのは、「学びは決して一人で成り立つものではない」ということです。IBは、多様な視点や問いを大切にし、深く考える姿勢を育てるユニークな教育体系だと感じています。しかし、その多くは私立校やインターナショナルスクールなど、限られた環境で実施されており、学費や家庭の支援なくして成り立たない一面もあります。だからこそ私は、こうした学びの機会を得られたことを当然とは思わず、支えてくれた家族や指導してくださった先生方への感謝の気持ちを忘れずにいたいと考えています。現在はIB教員として、生徒にも「学べることの尊さ」や「感謝をもって学ぶ姿勢」の大切さを繰り返し伝えています。学ぶことの喜びと責任を胸に、これからもも謙虚に、誠実に学び続けていきたいと思います。
